こんにちは。群馬県伊勢崎市にある「すずき歯科医院」です。

「子どもが受け口かもしれない」とお悩みの保護者の方もいらっしゃることでしょう。「子どもの受け口は放っておけば自然に治る?」「受け口の治療を始める時期はいつ?」など、悩むことはありませんか。受け口は、できるだけ早いうちに治療を始める必要があります。
この記事では、受け口になる理由や放置するリスク、治療をはじめる時期などについて解説します。

受け口は、奥歯を噛み合わせた状態のときに、下の前歯が上の前歯よりも突き出している状態のことです。通常であれば、奥歯を噛み合わせると、上の前歯が下の前歯を少し覆います。専門用語では下顎前突や反対咬合と呼びますが、見た目から受け口と呼ばれることが多いです。

ここでは、子どもが受け口になる3つの原因について、詳しくみていきましょう。
下顎が大きい、上顎が小さいなどの顎の骨格は、受け口の原因になり得ます。骨格的な要素は、両親から遺伝する場合もあります。また、下の歯の大きさが大きかったり、歯の数が多かったりすると、歯が並びきれず前に出てくるように生えるケースもあります。
上の歯が小さかったり、本数が足りなかったりすると、下顎の骨格の形状や歯並びに問題がない場合でも、受け口のように見えることもあるでしょう。受け口は、骨格や歯並びが関係していることが少なくありません。
指しゃぶり、爪を噛む、舌で前歯を押すなど、癖が原因となって歯を動かし結果的に受け口になる方は少なくありません。たとえば、指しゃぶりをしていると、前歯を外側に傾ける力が働きます。
また、舌で前歯を押して遊ぶ癖がある場合も、受け口になるリスクが高くなるでしょう。
口呼吸することが癖になっている場合、受け口になるリスクが生じます。口呼吸の場合、口周辺の筋力が落ちたり舌の位置が変わったりするため、下顎の成長に影響が出るのです。
通常、口を閉じた状態のときは、舌の先が上顎の前歯の裏側付近の歯茎へ付いています。口呼吸の場合、舌が下顎のほうへ落ちてきます。このため、舌が下顎を押して必要以上に大きく成長したり、下の歯を押し出したりするため、受け口になりやすいのです。

子どもの受け口を放置すると、見た目だけでなく成長に影響が出るリスクがあります。この項目では、受け口がどのような影響を与えるのか詳しくみていきましょう。
受け口であると、顎が突き出たように見えたり、下の歯が目立ったりするため、コンプレックスになる可能性があります。そのため、見た目を気にせずに笑ったり、みんなと会話したりするのを難しく感じるようことも少なくありません。
特に、子どもの成長に従って顎の成長が進むと、受け口がさらに目立つこともあります。成長とともに、子どもが外見を気にする可能性も考えられるでしょう。
受け口だと、舌が正しく動かせなかったり、口の構造に問題があったりすることが多いため、発音が悪くなるリスクが高いでしょう。また、受け口で口の構造に問題があると、正しい舌の使い方をした場合でも正しく発音できない可能性があります。
受け口は、噛み合わせや歯並びに問題がある状態のため正しく咀嚼できません。たとえば、食べ物を噛み切るのが難しいこともあるでしょう。前歯が適切に働かないと、奥歯にも負担がかかります。
さらに、奥歯もしっかり噛み合っていないケースの場合、食べ物を小さく咀嚼するのが難しいです。そのため、食べ物を丸呑みする習慣がつく可能性があります。胃腸に負担がかかり、消化不良や下痢・便秘などを引き起こすこともあるでしょう。
また、しっかり噛む習慣がないと、唾液の分泌量が減ります。唾液には、口腔内に入ってくるウイルスを除去したり、消化を助けたり、口の中をきれいにしたりする働きがあります。
それらの働きがなくなると、風邪をひきやすくなったり、虫歯になりやすくなったりと、全身の健康にも影響が及びかねません。

子どもの受け口の治療は、気がついたらできるだけ早くはじめるのが良いとされています。受け口は放置していても良くならず、成長とともに症状が悪化する可能性があるからです。少しでも気になる症状がある場合は、できるだけ早く歯科医院へ相談しましょう。

子どもの受け口を治療する方法は、主に下記の3つです。子どもの受け口の症状や年齢、成長に合わせて適切な方法を選びます。また、場合によってはいくつかの治療を併用することもあるでしょう。
予防矯正は、口腔内の正しい成長を促す目的で治療を行います。主に、下記の器具を使って受け口の原因となる癖を改善したり、口や舌の筋肉の機能が正しく動かしたりするトレーニングを行います。
成長過程にある子どもの場合、口周辺や舌の筋肉が正しく発達するように導くことで、ある程度歯並びが整う可能性が少なくありません。特に、後天的な原因で受け口になっている場合は、早い段階で予防歯科に取り組めば症状が改善されるでしょう。
急速拡大装置は、入れ歯のような形をした固定式の装置で、歯を外側に広げる働きがあります。取り外し式の拡大装置との違いは、拡大装置が歯を外側に広げるものであるのに対し、急速拡大装置は顎の骨の成長そのものを促進することです。
インビザライン・ファーストは、混合歯列期の子どもの矯正に特化したマウスピース矯正です。歯の移動とともに顎の成長も促すことが特徴です。
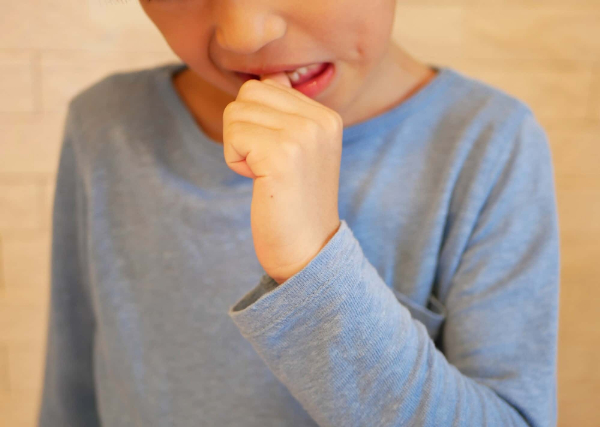
子どもが受け口になるのを防ぐためには、後天的な原因をできるだけなくすことが大切です。この項目では、具体的にできる方法について考えましょう。
指しゃぶりや爪を噛む癖、舌で前歯を押し出す癖などがある場合は、できるだけ改善しましょう。
ただし、指しゃぶりや爪を噛む癖は、精神を安定させるためにすることがあります。特に、指しゃぶりは、ある一定の時期までは口周辺の発達を促進する働きもしています。
また、幼い時期に指しゃぶりをしていても、徐々に収まることも少なくありません。3〜4歳頃までは様子を見て、子どもの状態にあわせて徐々にアプローチしましょう。
口周りや舌の筋肉が正しく発達するようにトレーニングすることは、受け口を予防する1つの方法です。たとえば、舌の先を正しい位置にあててポンと鳴らしたり、口をすぼめて前に突き出したりしてみましょう。
一緒に遊びながら行い、口周りの筋肉を鍛えましょう。また、歯科医院では、歯科医師や歯科衛生士が子どもの成長に合わせてトレーニング法をお伝えすることも可能なので、気軽に相談してみてください。
口呼吸の癖があると、受け口をはじめ、さまざまな健康上の問題が起こりやすくなります。できるだけ改善できるようにしましょう。口のトレーニングを続けることで、口の筋肉が発達すると、口を閉じた状態を保ちやすくなります。
しかし、鼻腔炎や花粉症、蓄膿症などの理由で鼻が詰まり、鼻呼吸が難しい場合も少なくありません。その場合は治療を優先する必要があるでしょう。
歯科医師と相談しつつ、口呼吸を辞める方法を見つけましょう。

受け口の原因は、骨格や歯並びなどが関係することもありますが、指しゃぶりや舌使いなどの癖が関係していることも少なくありません。受け口を防ぐためには、まず受け口の原因を知ることが大切です。
そして、原因や子どもの成長に合わせて、早めに治療を開始することが重要です。治療法は複数あるので、口腔内の状況や、成長にあったものを選ぶ必要があります。
子どもの受け口の治療を検討されている方は、群馬県伊勢崎市にある「すずき歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、自分の家族にできない治療はしないことを意識しながら、さまざまな診療を行っております。ホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
copy right Suzuki Dental clinic