こんにちは。群馬県伊勢崎市にある「すずき歯科医院」です。
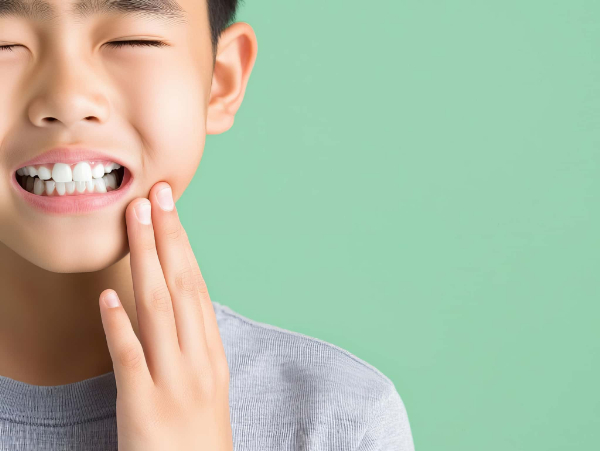
子どもの歯茎が赤く腫れたり出血したりしていませんか。それは、歯肉炎のサインかもしれません。歯肉炎は大人の口腔トラブルというイメージが強いかもしれませんが、実は子どもにも起こりうる症状なのです。
本記事では、子どもの歯肉炎の種類や予防のポイントを詳しく解説します。

歯肉炎は、歯周病の初期段階です。歯と歯茎の境目にたまったプラーク(歯垢)に潜む細菌が、歯茎に炎症を引き起こします。歯肉炎の段階では、歯を支える骨などの組織にはまだ損傷がなく、適切なケアによって改善が可能です。
歯肉炎の主な症状としては、歯茎の赤み、腫れ、歯みがき時や噛んだ際の出血、口臭などが見られます。特に、歯ブラシが歯茎に触れたときに出血がある場合は、炎症のサインである可能性が高いでしょう。
歯肉炎の段階では痛みを感じないことも多いため、軽視されやすいですが、放置すると慢性化し、歯周炎へと進行して歯を支える骨が破壊される恐れがあります。

歯肉炎は歯周病の初期段階であり、炎症が歯肉に限局して起きるものです。子どもが発症する歯肉炎にはいくつか種類があります。
ここでは、子どもの歯肉炎の代表的な種類について見ていきましょう。
不潔性歯肉炎は、プラークの蓄積によって引き起こされる歯茎の炎症です。小さなお子さまや、歯磨きが上手にできない方に多く見られます。汚れが蓄積されることによって、歯茎が赤く腫れたり出血したりするようになります。
歯周ポケットの中にプラークが蓄積すると、口臭の原因にもなります。
萌出性歯肉炎は、乳歯や永久歯が生えてくる際に、歯茎が炎症を起こす状態のことです。歯が歯茎を押すため組織に刺激が加わり、赤く腫れたり少し出血したりすることもあります。
歯が生えてくることによる歯肉炎なので、歯が生え終わると自然に症状が落ち着くケースが多いです。歯が生えてくるたびに萌出性歯肉炎が起きる場合は、歯科医院で相談して必要な処置を受けましょう。
思春期に入るとホルモンバランスが変化しやすく、歯茎が炎症を起こしやすくなります。特に、歯茎の健康状態は女性ホルモンの影響を受けやすいので、男性よりも女性に多い歯肉炎といえます。
10代前半〜20代前半にかけて発症する歯周病のひとつです。歯周組織を破壊する歯周病菌が歯茎の炎症を引き起こします。
若年性歯周炎は、通常の歯周病よりも進行が早いため早急な治療が必要です。

子どもが歯肉炎になる原因は、次のとおりです。
歯肉炎の主な原因は、やはり歯磨きが不十分であることです。乳歯から永久歯に生えかわる時期には、口の中の環境が特に不安定になります。歯が重なって生えたり、隙間に汚れがたまりやすくなったりして、磨き残しが増えることがあります。
その結果、歯茎に細菌が入り込みやすくなり、炎症を引き起こすのです。
思春期に入ると、ホルモンバランスの変化により歯茎が敏感になりやすく、軽い刺激でも炎症が起こることがあります。また、学校生活や家庭でのストレスが重なると、免疫力が一時的に低下して歯茎の炎症が悪化することもあります。
例えば、受験勉強中に食生活が乱れたり、睡眠不足が続いたりすると、菌の繁殖が進みやすくなり、歯肉炎の症状が現れやすくなります。
歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくい部分が生まれます。しっかり磨けていない箇所に磨き残しがあると、その部分からプラークが蓄積されて歯肉炎を引き起こす可能性があるのです。
特に、出っ歯やすきっ歯によって歯ブラシが届かない箇所にプラークが蓄積されると、その周辺で細菌が繁殖することがあります。
日々の生活習慣も、歯肉炎の発症に大きく関わってきます。栄養が偏った食事や夜更かし、運動不足、ストレスなどは、体全体の免疫力を低下させ、歯茎が炎症を起こしやすくなる環境をつくります。
子どもは自分の健康状態を自覚しづらいため、周囲の大人が生活リズムや食事内容に気を配り、バランスの取れた食事や十分な睡眠を確保できるようサポートしてあげましょう。
唾液には自浄作用や抗菌作用があり、お口の中の汚れを洗い流したり細菌の繁殖を抑えたりする働きがあります。
しかし、口呼吸などによって口腔内が乾燥すると、唾液の効果が得られにくくなります。そのため、歯肉炎などの口内トラブルが発生しやすくなるのです。歯肉炎を予防するためには、鼻呼吸を意識すること、唾液の分泌を促すために酸味のある食べ物を摂ること、よく噛んで食べることが大切です。

子どもの歯肉炎は一時的な痛みや違和感で終わることもありますが、そのまま放置するとさまざまなリスクが生じます。歯肉の炎症を軽視すると、口の中だけではなく全身の健康にも悪影響を与える可能性があるのです。
ここでは、歯肉炎を放っておくリスクを解説します。
歯茎に炎症が起こると、痛みや圧痛が感じられ、何を食べても痛い、歯ブラシを当てるとズキズキするなどの症状が現れる可能性があります。歯磨きをする際の不快感から、歯磨きがさらに難しくなることもあるでしょう。
歯肉炎が進行すると、顎の骨に影響が出て、支えを失った歯がグラつくようになります。そのまま放っておくと、最終的に歯を失う可能性があるのです。
子どものうちに歯を失うと、顎の発育に支障をきたしたり、発音が不明瞭になったりするケースもあるでしょう。将来的に大掛かりな治療が必要になる可能性があるため、早期に対応する必要があります。
歯肉炎を放置すると、治療が長引く可能性があります。初期段階であれば、歯科医師によるクリーニングや正しいブラッシング方法の指導によって改善が期待できるでしょう。
しかし、炎症が悪化して膿がたまるような状態になると、治療に時間がかかるようになります。場合によっては、麻酔をして膿を排出したり、外科的な処置が必要になったりすることもあるのです。複雑な治療が必要になると、お子さまやご家族の負担も大きくなります。
歯肉炎による口臭は、本人にとって大きなストレスとなります。「口が臭う」と友だちに指摘されたり、恥ずかしいと感じたりすることで、学校生活に消極的になる子どももいます。笑ったときに手で口を覆うようになるなど、心理的な影響が現れることもあるでしょう。
歯茎の炎症によって口臭が発生すると、本人が気にするケースがあります。学校や友だちとの関わりで不安を抱えたり、自己肯定感が下がったりすることもあるでしょう。
さらに、歯茎の腫れや痛みのせいで笑えず、笑顔が減るお子さまもいます。お口周りのトラブルが原因で、他人とのコミュニケーションでストレスを抱えたり、笑顔を隠したりすることもあるのです。

子どもの歯肉炎を防ぐためには、日常生活のなかでの心がけが大切です。ご家庭でできる予防法を、以下で確認しましょう。
子どもが自分で歯を磨くことを習慣づけるだけではなく、歯磨き指導を受けながら正しい歯磨きの仕方を学ぶことが大切です。歯科医院でブラッシング指導を受けることにより、歯と歯茎の境目の磨き方や、力の入れ方を教えてもらえます。
歯茎を傷つけてしまうような磨き方ではなく、やさしいブラッシングを取り入れましょう。
子どもの歯肉炎を予防するためには、定期的に歯科検診を受けることが大切です。家庭でのケアをどれだけ丁寧に行っていても、磨き残しは発生するためです。
ふだんの歯磨きでは除去できない汚れを除去するためには、歯科医院でクリーニングを受ける必要があります。また、歯科医院で受ける検診では虫歯や歯肉炎の兆候がないかチェックすることができます。
また、歯肉炎をはじめとしたお口のトラブルは初期症状が出にくいです。特に、子どもの場合は症状に気づくのが遅れやすいため、早期に発見して治療・予防につなげることが重要です。
さらに、検診を定期的に受けておくと、お子さまの歯並びや噛み合わせの状態も歯科医師がチェックできます。検診を受けた際には、ブラッシング指導も受けられるでしょう。
お菓子やジュースなど糖分の多い食品を頻繁に摂取していると、口腔内が酸性に傾き、細菌が繁殖しやすくなります。歯茎の健康を維持するためには、糖分の多い食品を摂取するタイミングに気を付けることも大切です。
例えば、お菓子を食べたりジュースを飲んだりした後には歯磨きを行いましょう。
歯肉炎の原因となる細菌は、砂糖をエサとして増殖します。おやつを食べたあとは歯磨きの時間を設けるなど、プラークの蓄積を防ぐことを意識しましょう。1日に何回もおやつを食べる習慣がある場合には、間食の回数を減らしたり、おやつの時間を決めたりすることも必要です。
また、就寝中は唾液の分泌量が少ないため、就寝前の歯磨きや水分補給はしっかりと行うようにしましょう。

子どもが歯肉炎になる原因は、歯磨きの不十分さや生活習慣の乱れなど、身近な生活環境のなかに潜んでいます。歯茎の炎症を放っておくと歯周病が進行し、最悪の場合には歯を失う可能性もあるのです。
しかし、早期に気づいて適切なケアを行えば、症状を改善することができます。お口の健康を守るためには、日常的なケアと定期的な歯科検診の両立が重要です。また、お子さまの成長段階に応じて、歯科医師のアドバイスを受けながら対策を進めていきましょう。
子どもの歯肉炎を予防したい方は、群馬県伊勢崎市にある「すずき歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、自分の家族にできない治療はしないことを意識しながら、さまざまな診療を行っております。ホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
copy right Suzuki Dental clinic